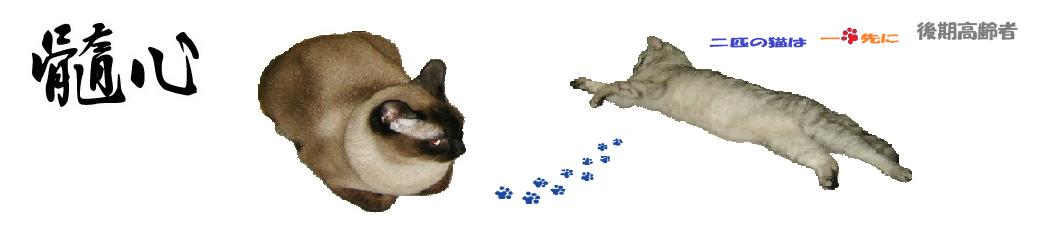中学校の三年間で習う、1110文字の内の5つの漢字を書いています。漢字は2020年度施行の学習指導要領に対応しています。
表示は左端が対象漢字、続いてカタカナは音読み、平仮名は訓読み、画数、部首の順です。そして、ことわざ・故事・文章などから一つを選んでその漢字の使われ方を示す事にしました。
ちなみに、文部科学省では学年ごとに習う漢字は、1学年250字程度から300字程度、2学年300字程度から350字程度、3学年では、その他の常用漢字(小学校で習う漢字1026文字以外の常用漢字1110文字の大体)と学年ごとに決まっていないようです。
501. [畳][ジョウ][たた-む][たたみ][画数:12画][部首:田]
『起きて半畳寝て一畳 天下取っても二合半』
このブログの『文武両道のために・・・・『徒然草』を読んで見る。』に次のように掲載しました。
『「起きて半畳寝て一畳たらふく食っても二合半」が記憶にありますが、これは、記憶の間違いで「起きて半畳寝て一畳」と「天下取っても二合半」と言うらしいです。
記憶というものは不確かなもので、徳川家康の言葉と思っていました。織田信長の言葉らしいですが、他にも、豊臣秀吉、夏目漱石、内田百閒などの説もありますので、誰が言ったのか不明としておきましょう。』と掲載しました。
この言葉「天下取っても二合半」でも「たらふく食っても二合半」にしても、所詮はその程度のものだという事では無いでしょうか。
もちろん、人間の欲望は際限ないように見えます。欲が頭の隅をかすめたら、この言葉を思い出して見るのも良いかと思っています。
確かに定かではありませんが、私は徳川家康が遺した言葉であれば、その意味も価値あるものと思っています。
夏目漱石や、内田百閒であれば、その意味する所も変わってきます。私は、織田信長や豊臣秀吉、あるいは徳川家康の言葉として聞いておきたいと思います。
楷書 |
行書 |
草書 |
502. [壌][ジョウ][画数:16画][部首:土]
『土壌汚染』
直ぐに東日本大震災の放射能による土壌汚染が思いつきますが、土壌汚染はもっと前からありました。
最近では、豊洲市場の土壌汚染も話題に上りました。
私が耳にした最初だと思うのですが、「イタイイタイ病」から始まり「水俣病」、「六価クロム汚染」、そして放射能汚染です。
それからこれは土壌汚染と言えるかどうか分かりませんが、ダイオキシンによる汚染も見逃す事ができません。
もともと農地に対して言われていた言葉だと思いますが、今では土壌、すなわち生物に影響を与える地表に、重金属、有機溶剤、農薬、油などが含まれている事を言います。
自然的にある物は別にして、産業が発達する段階で垂れ流しになった物も多くあると思います。
人間は土地と同様、地球は借り物であると認識すべきかも知れません。
楷書 |
行書 |
草書 |
503. [嬢][ジョウ][画数:16画][部首:女]
『お嬢吉三』
「月も朧に白魚の篝も霞む春の空 冷てえ風もほろ酔いに心持ちよくうかうかと 浮かれ烏のただ一羽ねぐらへ帰える川端で 竿の雫が濡れ手に泡思いがけなく手に入る百両 ほんに今宵は節分か西の海より川の中 落ちた夜鷹は厄落とし 豆沢山に一文の銭と違って金包み こいつぁ春から縁起が良いわい」これは歌舞伎のセリフですが、最後の「こいつぁ春から縁起が良いわい」と言う言葉は、一度位は耳にした事があるのではないですか。
このセリフ、七五調で、季節感あふれる言葉が連なり、演じる役者も歌うように言う名場面です、作者の河竹黙阿弥の得意といする所でしょう。
同じ作者の「白波五人男」その登場人物「弁天小僧菊之助」は、美空ひばりさんや三浦洸一さんの歌にもなりましたが、歌舞伎の名セリフ「知らざあ言って聞かせやしょう 浜の真砂と五右衛門が歌に残せし盗人の 種は尽きねえ七里ヶ浜、その白浪の夜働き 以前を言やあ江ノ島で、年季勤めの稚児が淵・・・・」この辺りまで、小学校に上がる前に言っていた事を思い出します。しかし、どこで覚えたのでしょう。
楷書 |
行書 |
草書 |
504. [錠][ジョウ][画数:16画][部首:金]
『尾錠金』
 これ千年前のバックルですって。日本語で言うと尾錠、または尾錠金と言います。
これ千年前のバックルですって。日本語で言うと尾錠、または尾錠金と言います。
今や、バックルの方が定着しています。
ズボンだけでなく、色々な使われ方をしています。例えばバッグとか馬具にも、時計のベルトにも使われています。
歴史はこの写真のように古くからあったと思われますが、日本では意外と新しいと思います。明治の初期だという事です。丁度文明開化が叫ばれた時期でしょう。
楷書 |
行書 |
草書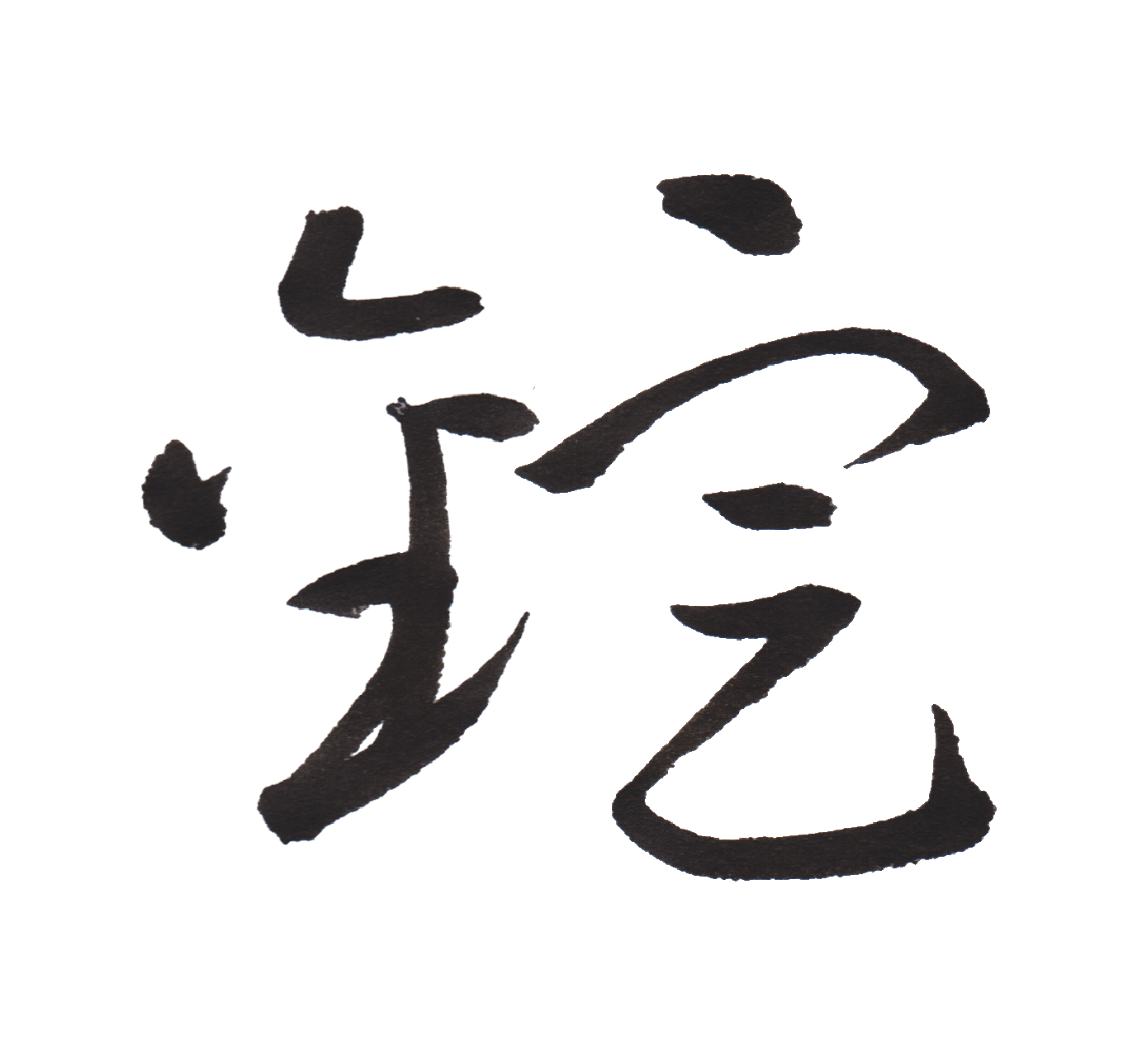 |
505. [譲][ジョウ][ゆず-る][画数:20画][部首:言]
『治安権限移譲』
法治国家では起こらないのですが、すでに法治出来ない状態になっている紛争地は、国連や多国籍軍によって統治されている状態と言えます。
多分少しは落ち着きを取り戻した状態で、現地の軍や警察に移すときにこの言葉を使うのでしょう。
国連や多国籍軍が統治出来ない場合、どうするのでしょう。
楷書 |
行書 |
草書 |