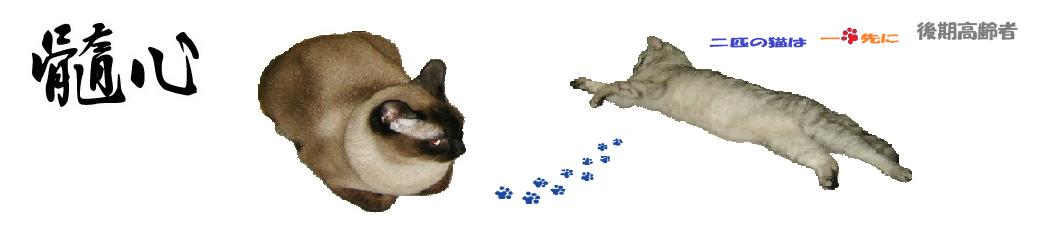中学校の三年間で習う、1110文字の内の5つの漢字を書いています。漢字は2020年度施行の学習指導要領に対応しています。
表示は左端が対象漢字、続いてカタカナは音読み、平仮名は訓読み、画数、部首の順です。そして、ことわざ・故事・文章などから一つを選んでその漢字の使われ方を示す事にしました。
ちなみに、文部科学省では学年ごとに習う漢字は、1学年250字程度から300字程度、2学年300字程度から350字程度、3学年では、その他の常用漢字(小学校で習う漢字1026文字以外の常用漢字1110文字の大体)と学年ごとに決まっていないようです。
616. [爽][ソウ][さわ-やか][画数:11画][部首:爻]
『秋高気爽』
「天高く馬肥ゆる秋」と言いますから、日本の秋は人々に爽快な気分を感じさせてくれると思います。それでも、次に来る冬を感じて嫌いな人もいるかも知れません。
松尾芭蕉の句に「この道や 行く人なしに 秋の暮れ」なんて秋の夕暮れの寂しさを詠ったものもあります。あるいは、同じ芭蕉が「枯れ枝に 烏がとまりけり 秋の暮れ」。
多分人それぞれに人生の中で、爽快な気分の秋と、うらさびしさを感じる時、どちらも経験していると思います。
楷書 |
行書 |
草書 |
617. [喪][ソウ][も][画数:12画][部首:口]
『禍福得喪』
「七転び八起き」と言いますから、人生は良い事も悪い事も起こると思った方が良いでしょう。
悪い事ばかり続いていると、そんな事も思えない時もあるかも知れません。
そんな時は、「人間万事塞翁が馬」と考え方一つで良くなる事もあると思います。
楷書 |
行書 |
草書 |
618. [痩][ソウ][や-せる][画数:12画][部首:疒]
『痩骨窮骸』
こんな骸骨のように痩せ衰えたくはありませんが、太り過ぎも良くありません。
生き方も、身体の様子もほどほどが良いと思います。
しかし、身長はどんどん低くなっていくのは、止めたいですね。
楷書 |
行書 |
草書 |
619. [葬][ソウ][ほうむ-る][画数:12画][部首:艸]
『蘭亭殉葬』
書道の大家に王羲之と言う人がいました。書聖と称される程の人です。その人が遺した書に蘭亭序と言うものがあります。
私が通信教育で受けた課題にも蘭亭序の一節が出されました。
この蘭亭序を自分が死んだときに一緒に埋葬するよう命令した唐の太宗の偏愛ぶりから出来た言葉です。
ですからこの言葉は、「書画などの骨董品を強く愛好し、執着すること。」【出典:四字熟語辞典ONLINE.】とあるように、ただの愛好家ではなく、執着しすぎる人の事を揶揄する言葉のようです。
楷書 |
行書 |
草書 |
620. [僧][ソウ][画数:13画][部首:人]
『非僧非俗』
これは親鸞が僧籍を外された時に言った言葉とされています。僧でも普通の人でもないと。
では、何なんでしょうね。
当時は身分制度がありますから、僧籍が無くても仏道を歩むと言う覚悟かも知れません。
今では、僧でもなく、普通の人でなくても、人間である事に変わりがありませんから、堂々と自分の信じた道を歩めると思うのですが。
楷書 |
行書 |
草書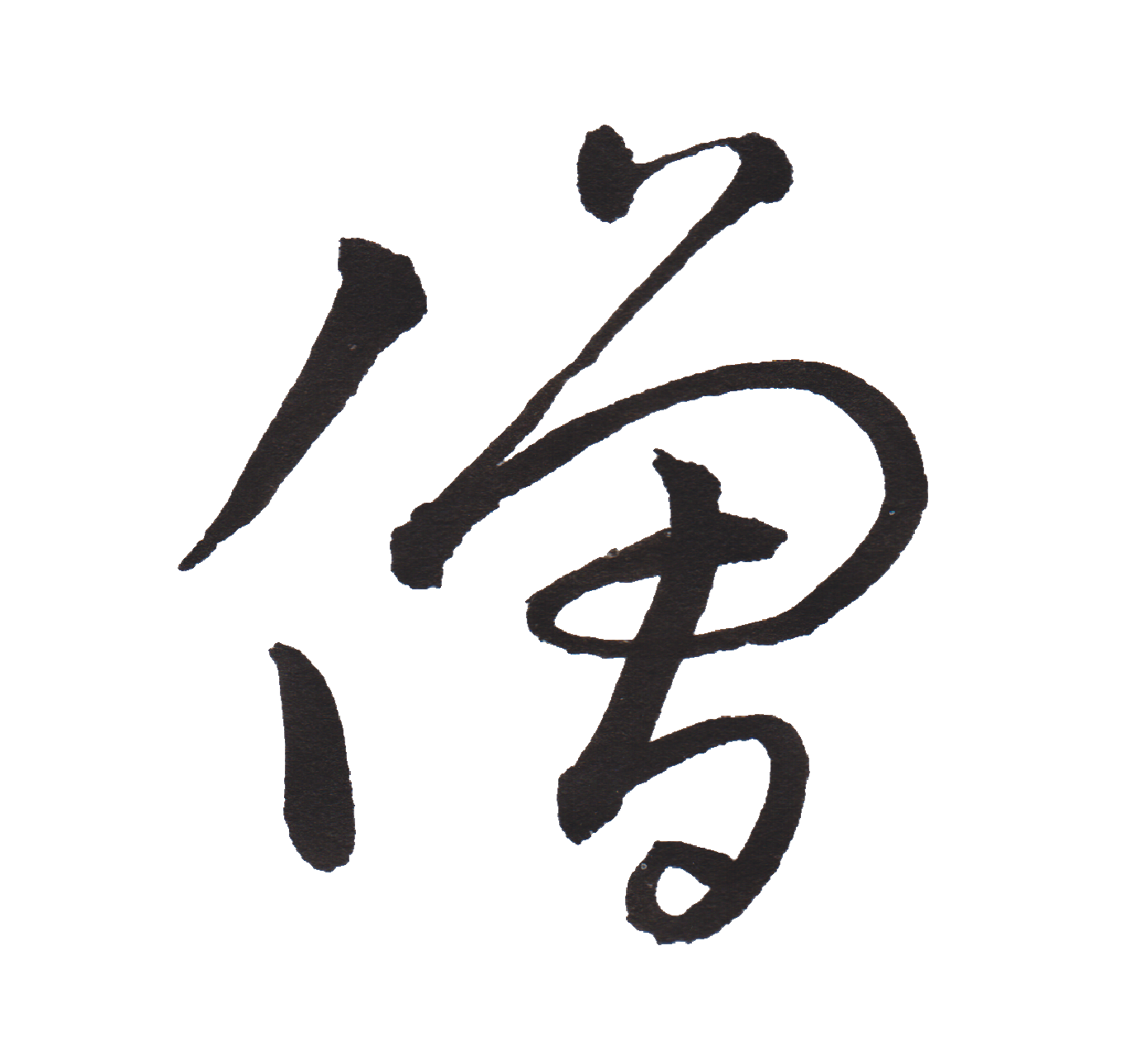 |