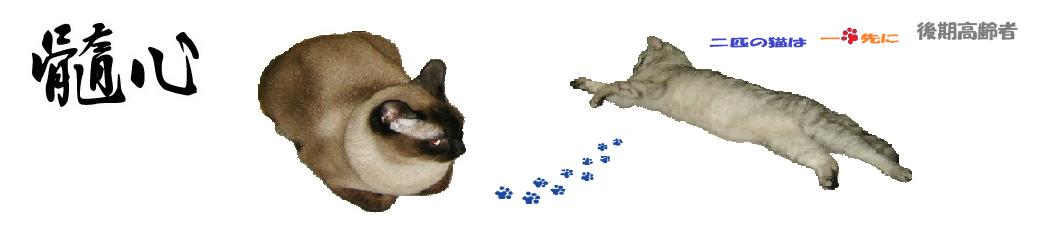| 【五輪書から】何を学ぶか? |
場所取りと言うと、桜見、運動会、会場選びなら忘年会など、色々幹事が苦労するところです。出来れば、参加する人に喜んでもらえるよう、色々な情報を集めて苦心することでしょう。
どこでも良さそうに思いますが、そうでもありません。場所によっては、後味の悪くなる時も、ままあるでしょう。
![]()

特に、そこで生死を決するという事であれば、尚更です。
生死を掛けないまでも、競技の試合場や昇段審査の会場、あるいは演武する場所などは、前もって確かめて置く位の準備はあっても良いと思います。
私は、昇段審査の前の日に会場に行き、稽古をする分けではないのですが、裸足で床の感じを確かめていました。また、演武する時も同様です。もし、それが出来ない場合は、経験のある人から床の状態を聞きました。
行き当たりばったりは、見かけは男らしい印象を受けますが、勝負となると、男気だけでは、何ともなりません。結果、格好の悪い事にもなりかねません。
あまり神経質になるのではなく、習慣として些細な事にも注意できるようにしておく必要があると思っています。
と、出来た人のように書いていますが、ある審査会場で、トイレに入り、ズボンの紐が抜けてしまった事がありました。空手着のズボンは、そう簡単に紐を通すことが出来ない構造になっています。大慌てです。仕方なく後輩のズボンを借りて、審査を受けたことが喚び起こされます。今考えても恥ずかしい限りです。
【火之巻】の構成
|
1. 火之巻 序
2. 場の次第と云事 3. 三つの先と云事 4. 枕をおさゆると云事 5. 渡を越すと云事 6. 景氣を知ると云事 7. けんをふむと云事 8. くづれを知ると云事 9. 敵になると云事 10. 四手をはなすと云事 11. かげをうごかすと云事 12. 影を抑ゆると云事 13. うつらかすと云事 14. むかづかすると云事 15. おびやかすと云事 |
16. まぶるゝと云事
17. かどにさはると云事 18. うろめかすと云事
19. 三つの聲と云事
20. まぎると云事
21. ひしぐと云事
22. 山海の變りと云事
23. 底をぬくと云事
24. あらたになると云事
25. 鼠頭午首と云事
26. 将卒をしると云事
27. 束をはなすと云事
28. いはをの身と云事
29. 火之巻 後書
|
2. 場の次第と云事

戦う場の状態を見分ける方法は、戦う場所では陽を後ろにして構える事。もし、場所によっては陽を後ろに出来ない場合は、右の脇に陽が来るようにする事。
座敷でも、明かりを後ろ、又は右の脇に来るようにする。これは陽の場合と同様である。
後ろが詰まらないよう、左側も広く取り、右側を詰めて構えたい。
夜の場合は、相手が見える場所では、火を後ろにし、出来ない場合は右脇に明かりがあるようにする事、陽の場合と同じと心得て構えるべきである。
相手を見下ろすと言って、少しでも相手より高い所で構えるように心得るべきである。
座敷では、上座を高き所と思えば良い。
さて、戦いになって、敵を追い回す場合は、自分の左の方に相手が来るよう心掛け、難所を敵の後ろにさせ、どんな場合も、難所に追い込むようにする事が大切である。難所では、相手に状況を把握させないよう、相手に顔を振り向かせないようにし、油断なく競って詰める気持ちを持つ。座敷でも、敷居、鴨居、戸障子、椽(たるき)、また、柱などの方に追い詰めるにも、相手に見せないようにする。これも先述と同じである。
いずれの場合でも、敵を追いかける場合は、足場の悪い所、または、脇に支障のある所、どこでも場の有利に立ち、勝ちを得る事を優先に考える事を、よく心に置いて、鍛練するべきである。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
『私見』
「水之巻」では、毎日の練習カリキュラムと共に、一つずつの技術の要旨を書かれてあったと思います。この「火之巻」では、正に戦いを迎え、あるいは戦いの最中に対処する方法が書かれてあります。
初めに、「場所」を挙げている点は、流石に実戦を通しての着眼点と思います。
特に刀を使う場合は、場所を考えないと、振り回す事ができない場合もあるでしょう。相手にも自分にも不利な状態から、勝機を見つける事ができるのは、いち早く有利な状況に持っていく発想がなければなりません。

刀を使わない場合でも、陽を背にするのと、陽を直接見てしまう状況になるのとでは、雲泥の差があります。座頭市のように目をつむって戦えるなら別ですが、普通はそうも行きません。場を選ぶと言うのは、大変重要な事だと思います。
実際に突発的に戦いが始まる場合は、場所を選んではいられませんが、予防は出来ると思います。
今になって考えると、この平和な時代に可笑しい事かも知れませんが、喫茶店などで座る場所は、ずっと、壁を背にして、出来れば四隅に座る事を習慣にしていました。道路で角を曲がる時には、少し遠回りをして曲がります。学生時代からつい最近まで、そんな癖が抜けませんでした。
故笹川良一氏(財団法人全日本空手道連盟・初代会長)は、ある時雑談の中で、「ホームで電車を待つときは、一番前に並んではいけない、そして、足を揃えてはいけない、足を前後にして、ふいに押されても前に行かないようにしている。」このように言われていた事を思い出します。
武道を志す者は、常に準備を怠ることなく、用意周到でなければなりません。武道を志す者ではなくとも、現在の社会は、資本主義社会と言う、正に戦いの場ではないでしょうか。
ビジネスの社会でも、場の有利不利が結果に結びつくと考え、交渉の場では場所選びをします。交渉の場でなく、それがイベント会場であったり、祝賀会場であっても同じです。個人的には、同じ食事をするのであれば、気持ちよく食事できる場所が良いですね。一生に一回とされる、結婚式場選びも、同じ理由で選択するのではないでしょうか。やはり、失敗するより、出来れば良い結果を生みたいものです。
用意周到、油断大敵は、武道に限った事でもなさそうです。
【参考文献】
・神子 侃(1963-1977) 『五輪書』徳間書店.
・佐藤正英(2009-2011) 『五輪書』ちくま学芸文庫.
【参考サイト】
・播磨武蔵研究会の宮本武蔵研究プロジェクト・サイト「宮本武蔵」http://www.geocities.jp/themusasi2g/gorin/g00.html
|
|
|
|
|
|