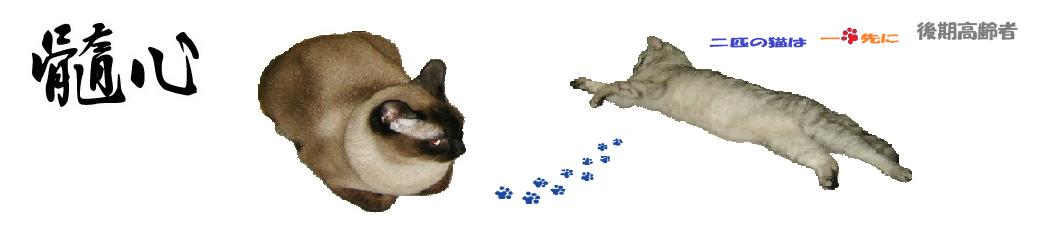中学校の三年間で習う、1110文字の内の5つの漢字を書いています。漢字は2020年度施行の学習指導要領に対応しています。
表示は左端が対象漢字、続いてカタカナは音読み、平仮名は訓読み、画数、部首の順です。そして、ことわざ・故事・文章などから一つを選んでその漢字の使われ方を示す事にしました。
ちなみに、文部科学省では学年ごとに習う漢字は、1学年250字程度から300字程度、2学年300字程度から350字程度、3学年では、その他の常用漢字(小学校で習う漢字1026文字以外の常用漢字1110文字の大体)と学年ごとに決まっていないようです。
601. [粗][ソ][あら-い][画数:11画][部首:米]
『褞袍粗糲』
何と難しい読み方でしょう。四字熟語は読めるだけでも凄いと思います。しかも、こんな言葉があると言う事を知るだけでも、勉強になります。
褞袍は、ドテラって読むそうです。ドテラは知ってます。綿が入った着物ですよね。これを粗末な衣類と言っていますが、私の印象はそんなに粗末とも思っていません。冬はとても暖かくて、今でもほしいくらいです。
「粗糲」は玄米の事だそうです。これを粗末な食事の代表のように言っていますが、まだまだもっと粗末な食べ物ってあるような気がします。
今では、健康食として玄米が重宝されていると聞きます。一時期私の家でも玄米や麦飯を食べて見ましたが、長くは続きませんでした。やはり白米が口に合うようです。
楷書 |
行書 |
草書 |
602. [疎][ソ][うと-い][うと-む][画数:12画][部首:疋]
『天網恢々疎にして漏らさず』
結構知っている人は多いのではないかと思います。老子の七十三章の最後に、「天網恢恢 疏而不失」と書かれています。その言葉では、「疎にして失わず」とありますが、意味は同じでしょう。
ここで言われている「天」は全てを見通している神であったり、自然と言う意味で解釈すれば良いかと思います。
ここでは天の神とでもしておきましょう。天の神の網は粗いように見えても、決して悪を見逃す事はない、そんな意味だと思います。
『天知る地知る我知る人知る』 に取り上げましたが、この時は言葉だけでした。他に何度かこの言葉を載せています。
この言葉のように天の神だけではなく、人間のする事は全てお見通しであると言う事でしょう。
楷書 |
行書 |
草書 |
603. [訴][ソ][うった-える][画数:12画][部首:言]
『訴求力』
「広告や宣伝が読者・視聴者など対象に訴える力。」【出典:大辞林第三版 三省堂.】。
私のイメージは裁判など、法律で使われると思っていました。違うのですね。
要するにビジネスの世界で、使われると言う事を知りました。
購買意欲を高める力とか、商品をアピールする、またはセールスポイントとでも言うのでしょうか。
楷書 |
行書 |
草書 |
604. [塑][ソ][画数:13画][部首:土]
『塑像』
「粘土・油土・蠟などを肉付けして造った像。銅像などの原型としても造られる。」【出典:大辞林第三版 三省堂.】。
私は今入れ歯を製作中です。最近は、制作手順が二つ増えたような気がしています。
前は、型取りして一週間くらいで、入れ歯が出来ていたと記憶しています。今回は、型取りの後で、噛み合わせ、そして、塑像というのかどうか分かりませんが、仮の歯が先日出来ていました。もう一度それを入れて噛み合わせを調整して、来週入れ歯が出来るようです。その間実に一ヵ月、それが済んだら、違う入れ歯を作ります。また一ヵ月かかるのでしょう。
像と言っても違いますが・・・・。
楷書 |
行書 |
草書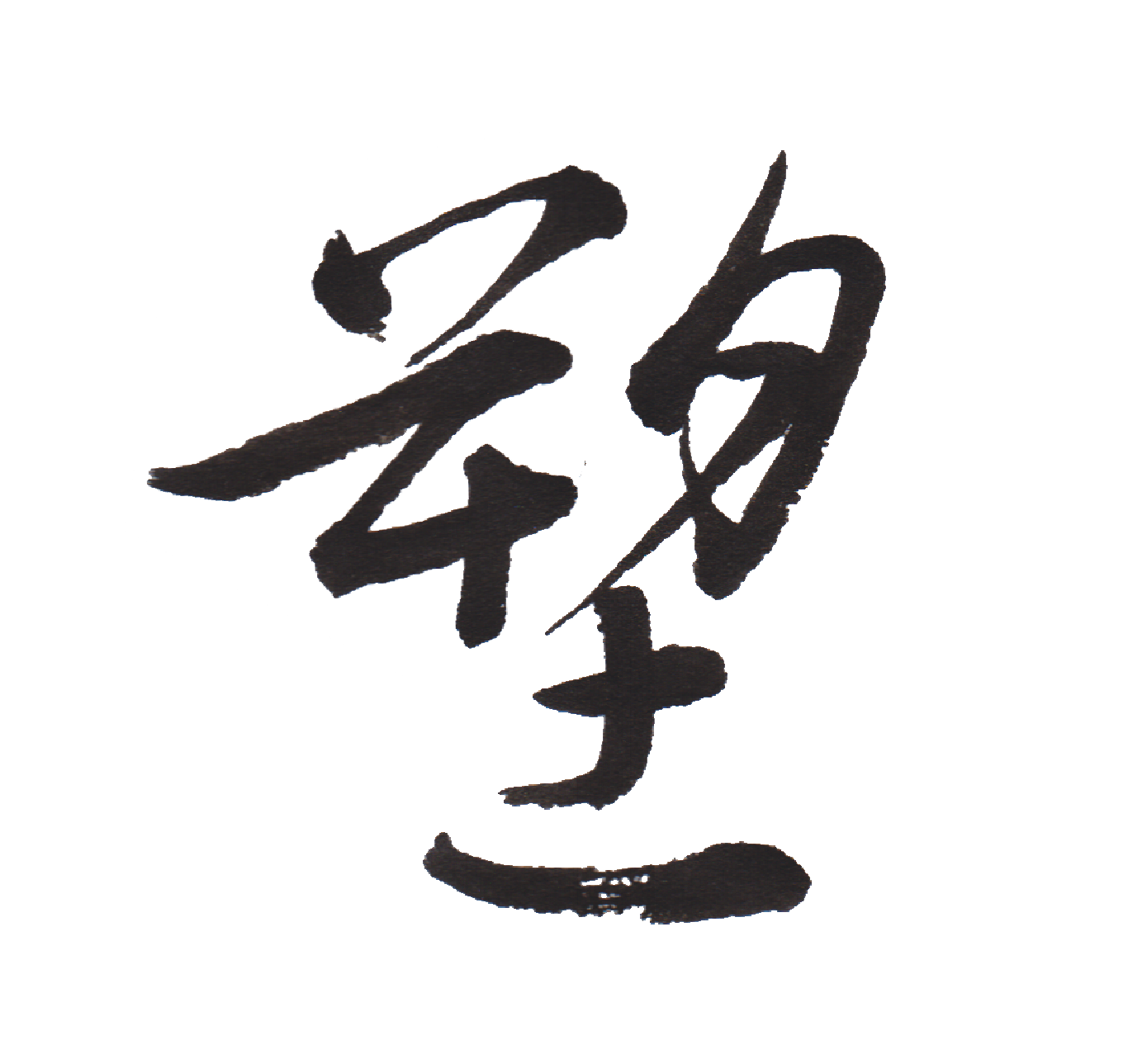 |
605. [遡][ソ][さかのぼ-る][画数:14画][部首:辵]
『遡及効』
一般的には法律上の言葉です。法律は原則、遡及しないのですが、場合によっては、遡って効力を発揮する場合もあります。
その遡及効がある法律は、民法にあります。
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第144条(時効の効力)時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
第506条二項 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
ではなぜ、憲法で定められている不遡及の原理を民法で覆しているのでしょう。
憲法には〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
と、刑事上について明記されています。よくドラマなどで言われている「一事不再理」ですね。
ここに書かれてある通り「刑事上」ですから、その他の法律では認められているのかも知れません。
しかし、法律で定められていない場合も、裁判の判決で認められる場合もあるようです。
楷書 |
行書 |
草書 |