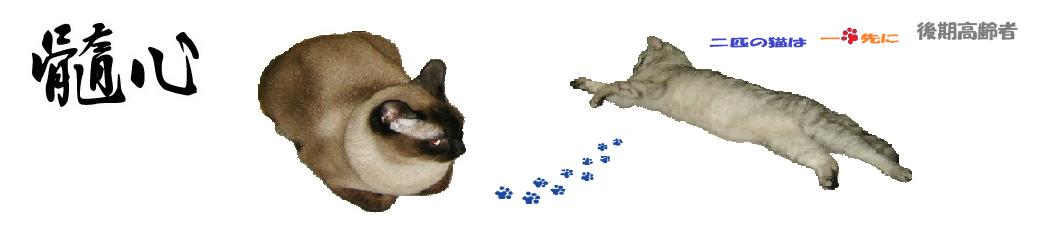中学校の三年間で習う、1110文字の内の5つの漢字を書いています。漢字は2020年度施行の学習指導要領に対応しています。
表示は左端が対象漢字、続いてカタカナは音読み、平仮名は訓読み、画数、部首の順です。そして、ことわざ・故事・文章などから一つを選んでその漢字の使われ方を示す事にしました。
ちなみに、文部科学省では学年ごとに習う漢字は、1学年250字程度から300字程度、2学年300字程度から350字程度、3学年では、その他の常用漢字(小学校で習う漢字1026文字以外の常用漢字1110文字の大体)と学年ごとに決まっていないようです。
611. [挿][ソウ][さ-す][画数:10画][部首:手]
『時の花を挿頭にせよ』
まず、挿頭を調べて見ましょう。「花や木の枝を折り、髪や冠に挿したもの。古くは、生命力を身につける呪術じゆじゆつ的な意味を持ったが、後に形式化し、造花を用いることが多くなった。」【出典:大辞林第三版 三省堂.】。
私は簪の事かと思いましたが、少し違うようです。
この諺、意味は、時の花ですから、時節に合ったものを使うと言う事から、時流に乗るのが世渡りのコツと言いたいのでしょう。
私の亡くなった友人、前にも書きましたが、結構大きな中小企業の社長が私に「風が吹かないとあかんねん」と言っていました。
確かに時流より早くても、時期尚早になりますし、遅れれば全く役に立たない事になります。世の中の波に乗るのは難しいですね。
楷書 |
行書 |
草書 |
612. [桑][ソウ][くわ][画数:10画][部首:木]
『滄海変じて桑田となる』
昔と違って、今では海を埋めて陸地にしていますから、この諺のように変化も尋常ではないと思います。
私が知っているだけでも、昔は浜辺だったところにマンションが立ち並んでいます。
この諺は、世の中の移り変わりの激しさを言っていますが、正にその通りだと思います。
それが自然であれば、人間には仕方のない事だと思えますが、わざわざ人間が自然を変えても良いのでしょうか。
楷書 |
行書 |
草書 |
613. [掃][ソウ][は-く][画数:11画][部首:手]
『内で掃除せぬ馬は外で毛を振る』
面白い譬えですね。これは子供の教育と言うか、躾けなんでしょう。
家庭の躾が悪いと、外でボロが出る。そんな意味で使われる様です。「お里が知れる」と言いますが、同じような事です。
別に家庭の躾だけでなく、日ごろの習慣が出てしまうのは当たり前のことだと思います。
すこし、襟を正して礼儀正しくしようとしても、付け焼き刃では思うような結果は得られないものです。
子供だけに限らず、大人でも日ごろから立ち振る舞いには気を付けたいものです。
しかし、この諺、家でしっかり面倒を見てやらないから、外にでて自分で対処しなければならない、とも取れますね。さて、どちらを言いたいのでしょうか。
楷書 |
行書 |
草書 |
614. [曹][ソウ][画数:11画][部首:曰]
『曹洞宗』
読み方は、ルビをふっているように「そうとうしゅう」です。
中国では禅宗五家(曹洞、臨済、※仰、雲門、法眼)の一つに数えられているものです。
日本では曹洞宗・日本達磨宗・臨済宗・黄檗宗・普化宗の五つが禅宗と言われています。
この曹洞宗は、鎌倉時代に道元が伝えたといいますが、曹洞宗を名乗ったのは道元が入滅後であったとされています。
曹洞宗は、「只管打坐」が主な修行方法で、道元が『普勧坐禅儀』を執筆して後世に遺した事も有名です。私が知っている『坐禅儀』とは違う物です。
特に有名なのは、年末に映し出される永平寺と總持寺を本山としています。
※さんずいへんに爲
楷書 |
行書 |
草書 |
615. [曽][ソウ][(ゾ)][画数:11画][部首:曰]
『曽参、人を殺す』
曽参は親孝行で名高い孔子の弟子です。その曽参が人を殺したと母親に告げたが、もちろん母親は信じなかった。しかし、三人から同じように言われて、母親は信じてしまった。そんな話が諺になったのでしょう。
「嘘も繰り返せば真実となる。」と言ったナチスドイツの宣伝相ゲッベルスの事は、前にも載せましたが、聞く方も違った三人から同じ事を聞くと、信じてしまうかも知れません。
しかし、親孝行で名高い孔子の弟子ですからね。信じる方もどうかしていると思います。
こんな気持ちになるのですかね。オレオレ詐欺の被害者は。
楷書 |
行書 |
草書 |