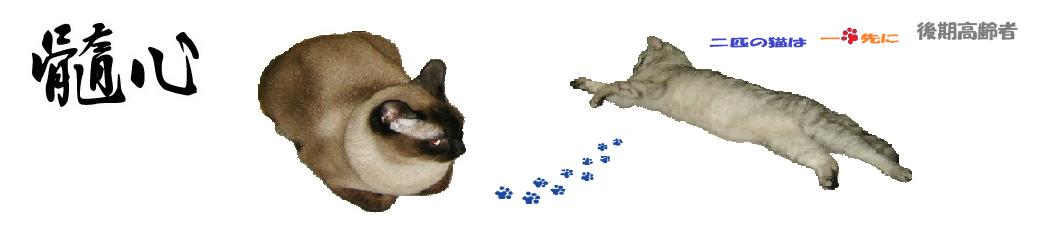中学校の三年間で習う、1110文字の内の5つの漢字を書いています。漢字は2020年度施行の学習指導要領に対応しています。
表示は左端が対象漢字、続いてカタカナは音読み、平仮名は訓読み、画数、部首の順です。そして、ことわざ・故事・文章などから一つを選んでその漢字の使われ方を示す事にしました。
ちなみに、文部科学省では学年ごとに習う漢字は、1学年250字程度から300字程度、2学年300字程度から350字程度、3学年では、その他の常用漢字(小学校で習う漢字1026文字以外の常用漢字1110文字の大体)と学年ごとに決まっていないようです。
631. [促][ソク][うなが-す][画数:9画][部首:人]
『拗促音』
この言葉は「拗音」と「促音」を一緒に言う時の言葉です。ですから、「拗音」と「促音」、二つの意味を知らなければなりません。私は残念ながら二つとも知りません。
と言う事でここでも辞書を引いて見る事にしました。
まず、「拗音」ですが、「日本語の音節のうち、「キャ」「シュ」「チョ」「クヮ」のように二字の仮名で書き表すもの。例えば、カ [ka] の子音と母音の間に、半母音 [j] が入ってキャ [kja] となり、半母音 [w] が入ってクヮ [kwa] となるの類。本来の日本語の音節にはなく、漢字音をとり入れたために生じたもの。ヤ・ユ・ヨを添えて表す開拗音と、ワ(ヰ・ヱ)を添えて表す合拗音との二種類がある。現代仮名遣いでは、前者は、イ段の仮名に小文字の「や」「ゆ」「よ」を添えて書く(「きゃ」「しゅ」「ちょ」など)が、後者は特にこれを表記することはしない。もっとも、歴史的仮名遣いでは、「く」「ぐ」に「わ」を添えて書く(「くゎ」「ぐゎ」の類)。」【出典:大辞林第三版 三省堂.】、「促音」については、「語中において、無声閉鎖音 k ・ t ・ p や無声摩擦音 s の前で一拍分だけ息をとめるものをいう。「かっぱ(河童)」「立った」「はっさく(八朔)」「バット」などのように「っ」「ッ」で表記する。つまる音。促声。」【出典:大辞林第三版 三省堂.】と書かれてあります。
なるほど、そう言う意味ですか。一つ勉強になりました。日ごろ何となく使っている日本語も、言い方が色々いあるのですね。
楷書 |
行書 |
草書 |
632. [捉][ソク][とら-える][画数:10画][部首:手]
『捉え処』
色々な人がいます。竹を割ったように、ハッキリしている性格の人、あるいは、優柔不断な煮え切らない人、ここで言われている捉え処のない、あるいは掴みどころのない人。
この中で一番始末に負えないのが、捉え処のない人ではないでしょうか。始末に負えないと書いてしまいましたが、理解の範疇を越えていると言った方が良いかも知れません。
この捉え処のない人にも、様々な種類があると思います。
一つは、自己中心的と言うのか自分勝手な人にもそんな所があります。人と合わせる気がありませんから、その言動を理解できない時があると思います。
二つ目は、自己中心的とちょっと違うのですが、信念のある人、これは良い意味で自立している人も、他の人から見ると捉え処がないようにも思えます。ですから、余り人の意見に引きづられない、付き合いの悪い人に見えるかも知れません。
三つ目は、何かの道に一心に取り組んでいる人も、同じように同調性や協調性に欠けると言えるでしょう。こんな人も何を考えているのか分からない事があります。
四つ目は、子供のように幼稚な人も、同じように捉え処のない立ち振る舞いをする事があります。天真爛漫とでも言いますか、社会通念に捉われないのでしょう。
五つ目は、よくテレビでこれを売りにしている天然と呼ばれる人です。テレビで見かけるのは、そんなキャラクターを売り物にしている思うのですが。
六つ目は、昼行燈と呼ばれる中村主水のような人。と言うとドラマの主人公ですが、何か裏で仕事をしていて、普通はその顔を見せない、二面性のある人。もしかしたら、そんな人があなたの隣にいるかも知れませんよ。
この人達に共通していると思われるのは、良くも悪くも人の意見に左右されず、独自の考えを持っているのかもしれません。
楷書 |
行書 |
草書 |
633. [俗][ゾク][画数:9画][部首:人]
『公序良俗』
大体どの辞書にも「公の秩序と善良の風俗。」と書かれていますが、どうも解りにくい説明と思います。
理由は公の秩序とは、余りにもボヤッとし過ぎていると思います。また善良も何が善で何が良いのかもハッキリ言えないのが世の中です。
にも拘らず、公序良俗に反する行為は無効とされています。難しい判断が要求される様です。
さまざまな判例によりその様子が分かります。
例えば金銭消費貸借契約の場合は、法律上なんの問題もありませんが、このお金を貸す場合、あるいは借りる場合に、その原因が賭博であるとか、脅迫などの場合に成立した契約の場合は、公序良俗に反する事になります。
今年の3月31日までは「第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」というものを、4月1日から下線部分を削除し、「第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と明確になるそうです。と言っても明確に理解する事は難しいのですが。
公序良俗と言うのは、言い換えれば、世間の常識です。しかし、これだけ世の中が変わっていく中で、常識もどんどん変わっていきます。
世間の常識、〇〇の非常識にならないようにしたいと思います。
楷書 |
行書 |
草書 |
634. [賊][ゾク][画数:13画][部首:貝]
『勝てば官軍、負ければ賊軍』
この言葉は、これまでも、歴史上何度かありますが、多くは明治維新以降に言われたのでしょう。
実際には、官軍ではなく、賊軍の幕府側であった人でも、大久保一翁や山岡鉄舟、勝海舟等優秀な人材は、新政府発足時の中心人物として活躍しているようです。
ただ、この言葉は、道理に適合しなくても、勝った者が正義と言う意味で使われる事が多いと思います。
世の中の大半の規律はこの言葉通りであると思いますが、理に適っていないものは、釈然としませんね。ま、その理が問題ですが。
楷書 |
行書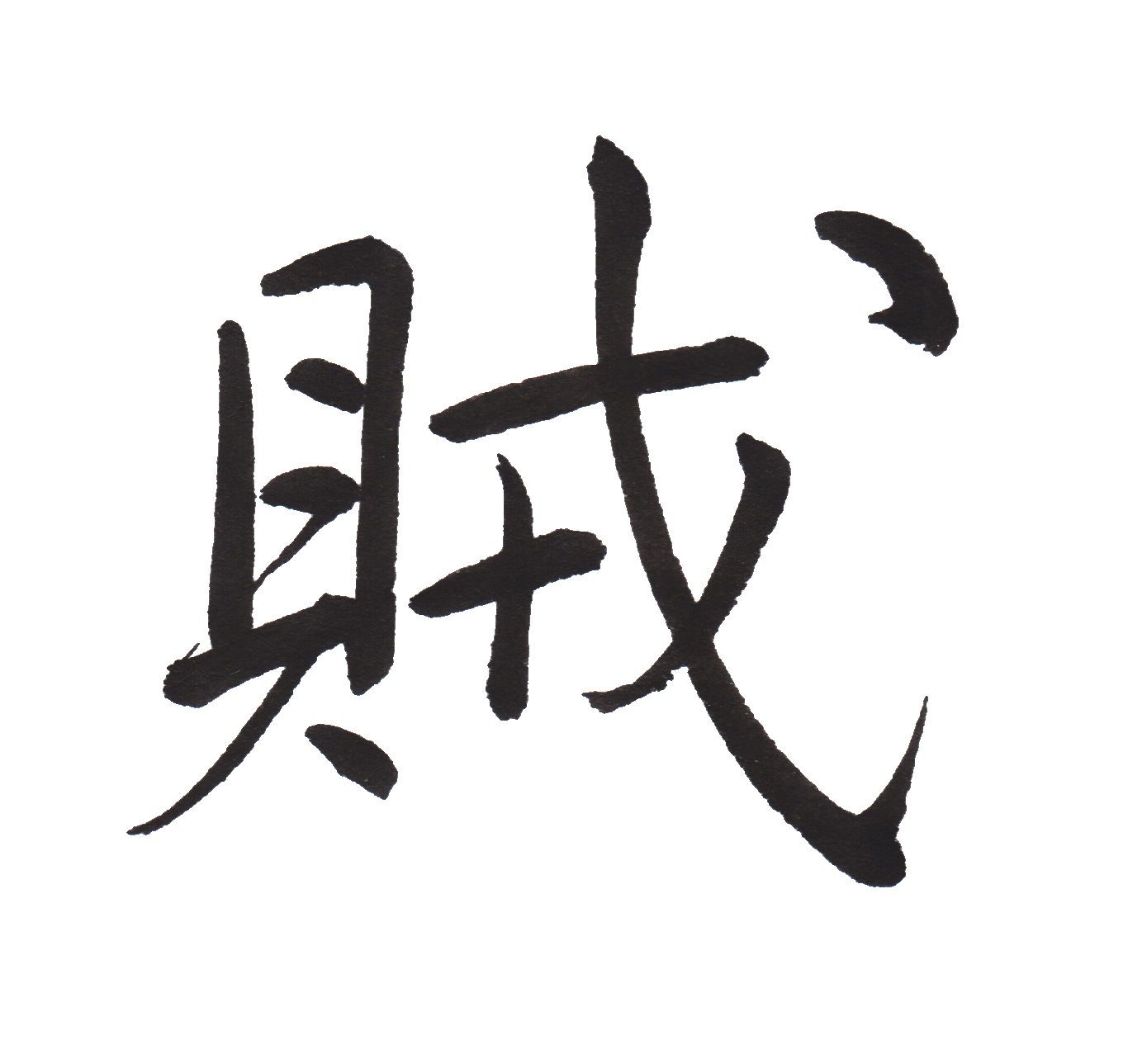 |
草書 |
635. [遜][ソン][画数:14画][部首:辵]
『謙遜語』
この言葉あまり耳慣れしないです。敬語の一つであるとは思いますが、敬語には尊敬語・謙譲語・丁寧語の3種類あるのが一般的だと思います。
辞書では謙譲語と謙遜語を同列に扱っているものが見られます。
しかし、平成19年2月2日に敬語の指針として文化審議会答申が出ています。その中には敬語の種類を5つに分類しています。「尊敬語・謙譲語Ⅰ・謙譲語Ⅱ・丁寧語・美化語」です。
その謙譲語について、次のように書かれています。
謙譲語Ⅰ( 伺う・申し上げる」型)自分側から相手側又は第三者に向かう行為・ものごとなどについて、その向かう先の人物を立てて述べるもの。
謙譲語Ⅱ ( 参る・申す」型) (丁重語)自分側の行為・ものごとなどを、話や文章の相手に対して丁重に述べるもの。
以上の詳しい内容は、次のURLを参照してください。https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai_6/pdf/keigo_tousin.pdf。
ただ、謙遜の意味は、自分の能力や功績などは表に出さず、むしろ遠慮がちな態度だと思いますので、言葉もそれに伴った言葉を使えれば良いですね。
楷書 |
行書 |
草書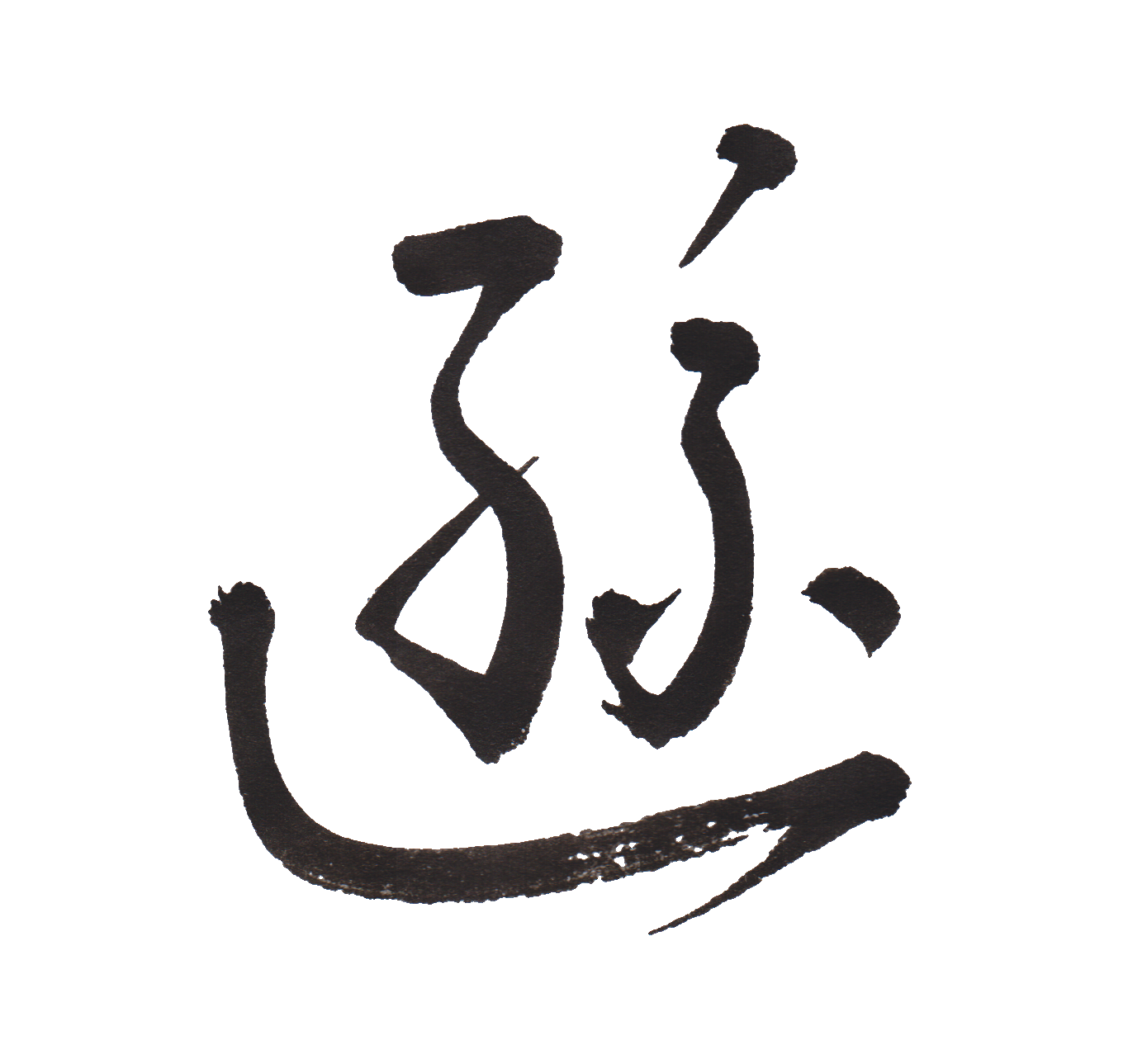 |