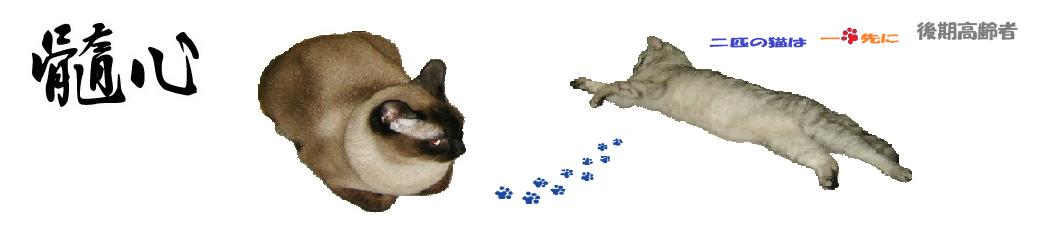ありました。学而篇1-1が。普通は、何が普通かも分からないのですが、この文章から始まる事になっています。しかし、全文を読むのは初めてです。
私の場合に限って言いますと、著者が言っているように、『この一章を正しく理解している人は少ない。』と書かれてある以前の問題です。
|
|
早速、白文と読み下し文を参考文献から引用してみましょう。
●白文
『子曰、学而時習之、不亦説乎、有朋自遠方来、不亦楽乎、人不知而不慍、不亦君子乎』。
●読み下し文
『子曰(のたまわ)く、学びて時にこれを習う、また悦(よろこ)ばしからずや。朋あり、遠方より来たる、また楽しからずや。人知らずして慍(うら)みず、また君子ならずや』。
「中学や高校で漢文を習い論語を教わる時」と『現代人の論語』には書かれてあるのですが、全くと言っていいほど、中学や高校で『論語』を習った記憶はありません。この著者は私より一歳年上ですが、何だか大昔の人のように感じます。教養の差ですかね。
初めての事ばかりで驚いていますが、この初めにある「学而時習之」の「学」と「習」という文字から「学習院」の名前が作られたそうです。ちょっとした蘊蓄(うんちく)になりそうですね。 「学而時習之」に対して、多くの現代語訳が間違っていると断言しています。どういう事かと言いますと、「時々」ではなく「時を選んで」と訳すのが正しいと言っています。その理由は、孔子と弟子は「礼」について学んでいます。著者は何度も『論語』を通読熟読されているので、他の章から推測されたのでしょう。孔子は「礼」と「楽」を、文化と解釈したようです。
「学而時習之」に対して、多くの現代語訳が間違っていると断言しています。どういう事かと言いますと、「時々」ではなく「時を選んで」と訳すのが正しいと言っています。その理由は、孔子と弟子は「礼」について学んでいます。著者は何度も『論語』を通読熟読されているので、他の章から推測されたのでしょう。孔子は「礼」と「楽」を、文化と解釈したようです。
ですから、「学びて時にこれを習う」の「時」を「モーツァルトの誕生日にバイオリニストやチェリストが集まって弦楽四重奏の練習をする」のように時を選んで習う、と解釈する事が正しいと書かれてあります。
『論語』の解釈は著者と私では雲泥の差があるとは思いますが、習うという事や「礼」については、少しは経験があります。
私は、間違った解釈と断言された「時々」でも、正しい解釈とされた「時を選んで」とも違うイメージを持っています。「礼」については四六時中、常住坐臥(じょうじゅうざが)、寝ても覚めても心に置き、表現し身に付けるものだと思っています。
であれば、この「時」は、刻一刻の時であり、常にと解釈した方が、私には納得できます。
また、ここには「楽」という文字はありませんが、他の章から鑑みて「礼」「楽」を文化と解釈する場合は、尚更の事、習い事ですから、時々では身に付きませんし、時を選ぶ場合は、演奏会のように披露する場ではないかと思います。これも演奏する者にとっては試みですから自分の為の練習にはなります。ですから、自分で練習する事も演奏会で演奏する場合も、その人にとっては同じです。反って人の前で演奏する事によって、学べる事も多くあります。ですから、刻一刻、常にどこでも時を選ばず稽古の場となります。
空手を例にしますと、船越義珍師が言われた「空手は湯の如し 絶えず熱度を与えざれば 元の水に還る」。この絶えずと言う所が、刻一刻だと思います。物事を習得するのに時を選ぶ事はないと思っています。
私がまだ若かりし頃、今よりずっと持久力があった時は、道場の練習から帰って来るのが夜の12時を過ぎていました。寝ても興奮が冷めやらず、直ぐに起きて1時過ぎまで練習した事もありました。ただこれは間違いであったと、反省しています。体力が続かず体を壊す事になりかねません。「湯の如し」が妥当で「熱湯」にして蒸発させてしまっては、元も子もありません。
ただ、これを人前で演武するとか、試合をするというのは、時を選ばなければならないでしょう。しかしこれはあくまでも稽古の一貫であろうと思います。
この「学而時習之」につづいて「不亦説乎」と悦ばしい事としているのは、正に常に習う事ができて、幸せな事を表しているように感じます。
生きていると、多事雑多、色々な煩わしい事に頭を悩ます事も多いと思いますが、稽古に汗を流している時、あるいは没頭できる環境を、悦ばしいと思うのは至極もっともな事だと思います。
私は仙人を目指していますので、あまり必要としませんが、「有朋自遠方来、不亦楽乎」にしても、同じ志を持つ者が集まったり、訪ねてきて嬉しく思わない人は、世捨て人か変人でしょうね。
その時代によって違いますが「礼節」などは、自分自身が身に付ける事で、人に強要するものでもなければ、まして、人に尊敬してもらうためや、立身出世のために身に付けるものでもありません。
私が思うのは、社会的な動物としての役割、生きていくための基本が『礼節』と思っています。
ですから、「人知らずして慍(うら)みず、また君子ならずや」の通りです。この「慍(うら)みず」は、弟子に言っている言葉で、参考文献にしている『現代人の論語』のように、孔子が人の無理解を嘆いている証拠とするのは、如何なものでしょう。
何度もこの言葉が出てくるらしいのですが、私はあくまでも弟子の中には、立身出世を志す人や、よこしまな考えを持つ人が多い事からの警鐘であったと思うのですが。
でなければ、聖人君主と言えないと思います。私はそのように考えたいと思います。
 たまたま現在は、文化的な活動、すなわち書、画、音楽などの芸術で生計を立てる事が出来る時代です。歴史を振り返ってみても文化的な営みが生計に直接結びつく事は少なかったように思います。生み出した人の気持ちとは関係のない所で価値を認められ、その時の為政者や権力者に丁重に扱われたのであって、絵画のように無くなってからその価値を見出す者がでてくる事も稀ではありません。
たまたま現在は、文化的な活動、すなわち書、画、音楽などの芸術で生計を立てる事が出来る時代です。歴史を振り返ってみても文化的な営みが生計に直接結びつく事は少なかったように思います。生み出した人の気持ちとは関係のない所で価値を認められ、その時の為政者や権力者に丁重に扱われたのであって、絵画のように無くなってからその価値を見出す者がでてくる事も稀ではありません。
人に認められたり、重用してもらう事を目的にした『礼節』『文化』は、決して孔子の言う、『礼』では無かったと思います。
【参考文献】
・呉智英(2003-2004)『現代人の論語』 株式会社文藝春秋.